中村健吾
研究者紹介
中村健吾 /教授 社会思想史
キーワード:欧州連合(EU)、福祉国家、グローバル化、シティズンシップ、人権
「グローバル化にともなう福祉国家とシティズンシップの変容」
国家理論からEU研究へ
私は国家理論の研究を目的にして1998年度にドイツのフランクフルト大学へ留学しました。その留学の最中に私は、ドイツ政府の政策を分析し評価するうえで、欧州連合(EU)の動向を視野に入れる必要性を痛感しました。そのため私の研究テーマは、国家理論からEU研究へと方向転換することになりました。
ドイツでの留学中に出会ったのが、EUを多次元的なネットワーク・ガバナンスのシステムとして捉えようとする研究アプローチでした。私はこのアプローチを応用して、EUという政体をもはや国民国家のモデルに基づいて理解するのではなく、むしろ帝国として把握することを提唱し、EUの分析を進めてきました(下の参考文献1など)。
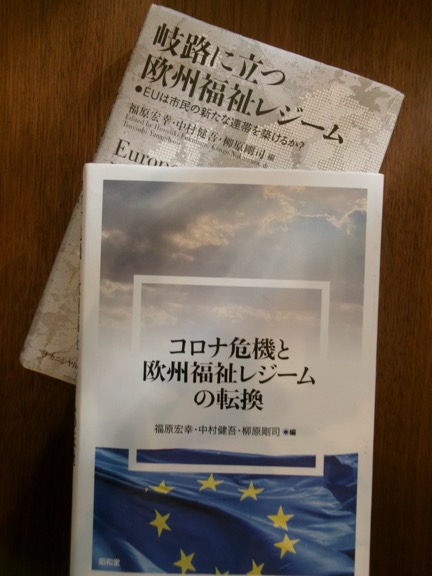
図1.EUに関する共著
欧州福祉レジームの変容に関する共同研究
私は2010年に「欧州福祉レジーム・市民権研究会」を起ち上げ、他の12名のヨーロッパ研究者とともに、EUとその加盟国における福祉レジームの変化を分析する共同研究を十数年にわたって続けてきました。この研究は、EUが直面したユーロ危機(2008年)、難民危機(2015年)、コロナ危機(2020年)などを節目にしつつ、下の参考文献2をはじめとする4冊の共著となって結実しています(図1)。
シティズンシップと人権
私が1993年に大阪市立大学経済学部へ「社会思想史」担当の教員として着任して以来、細々と続けてきたのが、シティズンシップと人権とを橋渡しするという思想史的研究です。この研究の出発点は、社会学におけるシティズンシップ論の現代的古典であるT.H.マーシャルの『シティズンシップと社会的階級』の共訳書を、私が1993年に公刊したことにありました(図2:下の参考文献3)。
しかし、「非市民」への排除を不可避的に伴うナショナルなシティズンシップは、国境を越える人の移動が常態化している21世紀の社会において、権利保障の面で深刻な限界を露呈しています。そのため、国籍に左右されない普遍主義的な人権の必要性が提唱されていますが、人権の妥当根拠をめぐって現代哲学は合意を見いだせないでいます。個別主義的なシティズンシップを普遍主義的な人権の理念に向かって開いていくための理論的な営みが必要になっています。
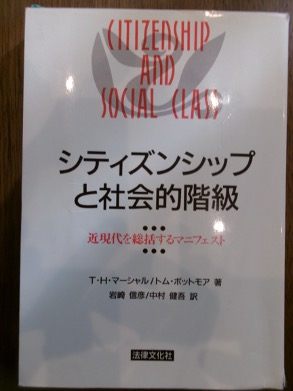
図2.シティズンシップ論
参考文献
- 中村健吾、『欧州統合と国民国家の変容:EUの多次元的ネットワーク・ガバナンス』、昭和堂、2005年。
- 福原宏幸・中村健吾・柳原剛司編、『コロナ危機と欧州福祉レジームの転換』、昭和堂、2023年。
- T.H.マーシャルほか著、岩崎信彦・中村健吾訳、『シティズンシップと社会的階級:近現代を総括するマニフェスト』、法律文化社、1993年。