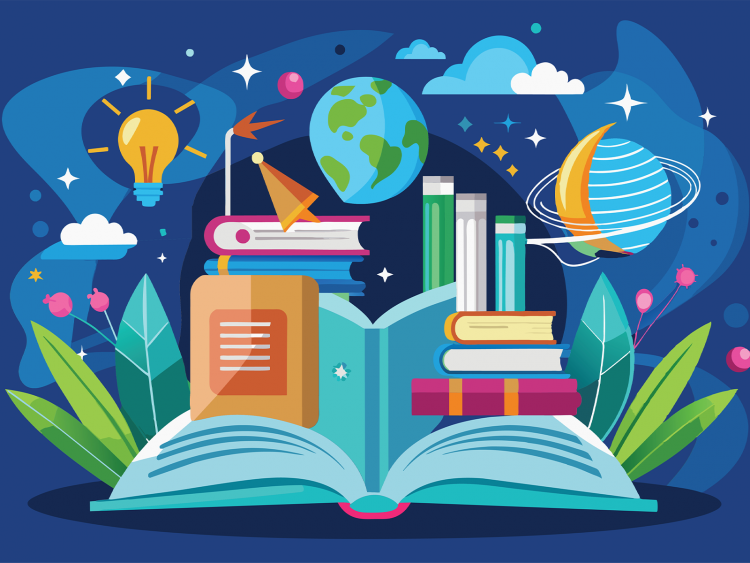自身の問題を学問に結びつける、ミシェル・フーコーの姿勢
大学に入るまでは、ずっと哲学を学びたいと考えていました。やはり自分自身、生きにくかったのでしょう。人間としてどう生きるかを考察することが哲学だと捉え、自然に惹かれたんだと思います。現代思想を専攻し、大学2年のころに感銘を受けたのが、ミシェル・フーコー※1という、セクシュアリティの研究をしていたフランスの哲学者でした。私が研究の世界に入っていったのは、フーコーの影響が一番大きかったです。フーコーの本も読みましたが、伝記とかを読んでフーコーの生き方に影響を受け、どうやって生きていきたいのかが固まったように思います。
彼は若いときに寮生活をしていて、自分が同性愛者なんじゃないかと気づきます。時代は戦後の1940年代。悩み苦しみ、自殺も図りました。そして気が狂いそうになったものの、自分の置かれている状況をどう考えればよいかに目を向け、狂気の研究を始めるのです。一般的には精神医学や心理学の分野で考えるところ、フーコーは狂人というのが歴史的にどのように生みだされたのか、歴史を遡って研究していきます。
フーコーは同性愛に関しても、100年前、200年前には社会でどう扱われていたのかを徹底的に調べています。同性愛に対する今の見方は歴史的につくられたものであり、時代や背景が違っていれば違う道を辿っていたかもしれない。どういう道になり得たのかを研究しようとしたわけです。同性愛が精神疾患かのように扱われるようになったのは何がきっかけだったのか。扱われはじめた地点まで遡り、病気ではないとされる別の道があったかを探していきました。そういう研究の方法にもすごく興味をもったし、歴史の研究をしているのだけれど実は自分自身のことを研究しているのがフーコーだと思いました。自分の問題と関係のないところで研究しても続かない、執着心がないと研究はできません。研究することによって自身の在り方も変われるのでは、と考える姿勢は、フーコーから学んだと思います。
卒業論文は、HIVについて書きました。最初はフーコーの晩年の思想を研究するつもりでしたが、フーコーが1984年にエイズで亡くなっていることもあって興味をもったのです。文化人類学の先生の勧めもあり、HIVに感染したゲイの人にインタビュー調査をしました。もともとは文化人類学はそれほど興味のある学問分野ではありませんでしたが、フィールドワークで探るという手法が自分の興味関心には最適だったため、だんだん面白くなり、今も研究のベースとなってます。そして卒論のHIVとゲイの研究からゲイ・スタディーズへ、そしてクィア・スタディーズ※2へとつながっていきます。
文化人類学は、今の私たちの価値観とは全く違う価値観で生きている人たちの生活を研究することなので、文化によって自分の「当たり前」と全然違う「当たり前」がある、いろんな価値観があるということに気づくことができます。自分の考え、価値観が絶対ではない、文化が変われば全く違う生き方をしている人たちがいるんだと分かること、それが文化人類学の面白さです。知っていることを追認するのではなく、知らないことを知ることができるのが、研究の面白さであり大変なところでもあります。
※1 ミシェル・フーコー(1926年10月15日~1984年6月25日):フランスの哲学者。著書に『狂気の歴史』(1961年)、『監獄の誕生』(1975年)、『性の歴史』(1976年)などがある。
※2 クィア・スタディーズ:レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーなど性の多様性を扱うための比較的新しい学問領域。
新ヶ江 章友教授の他の記事はこちら。
ジェンダー研究者が語る、今だからこそ考えたい多様な性との向き合い方
プロフィール

国際基幹教育機構/人権問題研究センター/大学院都市経営研究科 教授。
博士(学術)。カリフォルニア大学バークレー校人類学部客員研究員、財団法人エイズ予防財団リサーチレジデント、名古屋市立大学男女共同参画推進センター特任助教などを経て、2015年、大阪市立大学大学院に赴任。2022年より現職。専門は、ジェンダー/セクシュアリティ、文化人類学(医療人類学)、カルチュラル・スタディーズ。著書に『クィア・アクティビズム:はじめて学ぶ〈クィア・スタディーズ〉のために』(花伝社)など。
研究者詳細
※所属は掲載当時