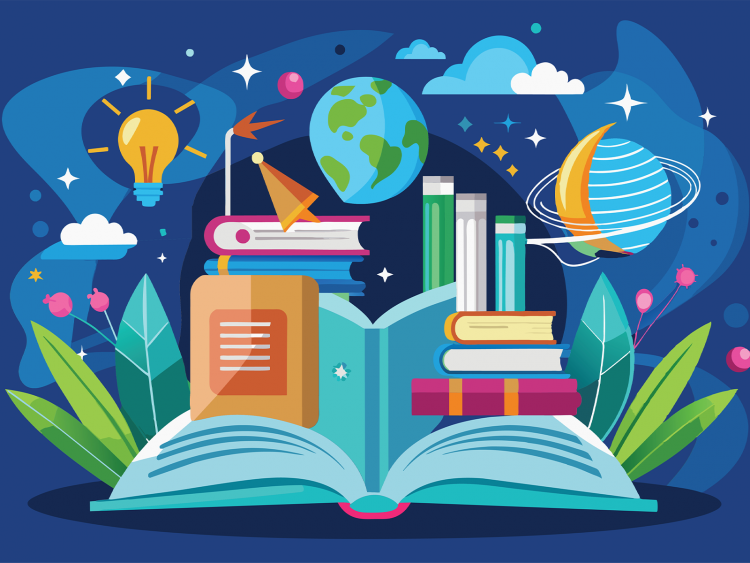3人もの師に導いてもらった私、「だから私がやるしかない」
振り返れば、幼い頃からの「博士ってなんかカッコいいな」という憧れに導かれて、研究者の道へと進んできたように思います。では、どのような研究者になりたかったのかと言いますと、研究テーマも子ども時代の関心が根底にあるようです。ものごころついてから、ずっと抱えていた疑問、それは「人間って、一体何なんだろう?」でした。
とにかく、いろいろな人がまわりにいる中で、いつも私は一歩引いた視点から、いささかクールにその人たちを見ていました。例えば、すぐ怒る学校の先生がいましたが、なぜそんなに怒るのだろうと不思議でした。かと思えば、私をほめてくれる人もいて、あの先生は怒るのに、この人はどうしてほめてくれるのだろうと考える。仲良しの2人組を見ていると、この2人が親友になった理由はなんだろうと知りたくなる。他の人とは違って、私の頭にすっと入ってくる話をしてくれる人がいると、この人の話はどこが、どのように違ったのかと考えたり。本当に人はそれぞれ違うんだと、人に対する興味が増していきました。
とにかく、対象はいつも「人」でした。だからたまたま広島大学のオープンキャンパスに行き、そこで出会った作業療法学の宮前 珠子先生から、「ここでは人間とは何かを学びます」と言われた時は「ここだ!」と直感で決めました。この先生が1人目の師です。ただ、大学で4年間学んだ時点では、研究に打ち込むためのテーマが見つからず、資格をとって作業療法士として働き始めました。
意識障害の方々のリハビリテーションに携わるなかで、自分の研究のコアとなるテーマが芽生えてきました。自分が向き合っている患者さんは意識障害ですから、私からの関わりには反応してくれません。だからといって患者さんたちは何も感じていないわけではなく、感じていて返したいと思っていながらも、ただ表現できていないだけではないのだろうか。
このテーマを追究したいと思い大学院に進み、意識障害の方々への作業療法に関する研究を始め、そこで2人目の師、広島大学の石附 智奈美先生に出会いました。先生が取り組まれていた神経発達症の子どものペアレントトレーニングに参加し、神経発達症の子どもや保護者との関わりを通じて、子どもたちが何を感じているのかがなんとなく分かるようになってきたのです。
世の中には支援を求めている人がいる。その人たちの声を世の中に届けるための研究ができる環境に自分がいる。そんな自覚を持つようになった私に、当時、大阪府立大学で教鞭を執っておられた高畑 進一先生から「この研究は、あなたがやるべきだよ」と言ってもらい、社会に還元できる研究に取り組もうと心を決めました。3人の師がかわるがわる私の背中を押してくれたからこそ、今私はここにいるのだと思います。
寄り添うことで見えてくる、神経発達症の子どもたちが生きやすい世界
プロフィール

リハビリテーション学研究科 講師
リハビリテーション学研究科 リハビリテーション学専攻 講師。
博士(保健学)。2022年より現職。2005年広島大学医学部保健学科卒業、2012年広島大学大学院保健学研究科博士課程前期修了、2020年大阪府立大学大学院総合リハビリテーション学研究科博士後期課程修了。自閉スペクトラム症の食行動に関する研究からスタートし、特別支援教育と作業療法、神経発達症児の支援などを含む学校コンサルテーションを行っている。
※所属は掲載当時