外国人労働者の受け入れ、これまでと現在
日本では戦後、商用目的で日本を訪れる外国人は増え続けましたが、公的には1980年代までは単純労働者の受け入れは行われていませんでした。その後、国内の人手不足が顕著になると、1990年に外国人研修制度が拡大され、就労を目的とした外国人の来日が全国的に急増。しかし、この時点ですでに受け入れ態勢には破綻の兆しがあったと明戸先生は指摘します。
「1990年に『外国人技能実習制度』の前身となる外国人研修制度が拡大され、名目としては『日本の先進的な技術を学び、国に帰ってそれを役立てる』という内容を打ち出していました。しかし、実際には政府が中小企業や個人の農家、漁業など人手不足の業種に人材を回す、すなわち海外から労働力を安く入れることを目的に制度が作られたため、最初から建前と中身が一致していなかったわけです。しかし業界からの要望は強く、『研修生が(期限である)1年で帰国すると困るから伸ばしてくれ』という声が上がるようになります。研修期間は伸ばせないから、以後は1年間の実習に移るということにして、2年間労働力として働いてもらう『外国人技能実習制度』が1993年に始まりました。
ただ、この制度は研修から始まったのが良くなかった。研修はもともとは留学の一種だから、それで日本に来る外国人は労働者ではないんです。研修だから12時間働かせても最低賃金すら払わないということがまかり通るし、ひどいものでは時給換算すると300円というケースもありました。技能実習制度では、『2年目から労働者としての権利を認めましょう』といわれるようになりますが、受け入れ側にその意識がないことも多く、結局そのまま同じ状況が続いていました」
外国人技能実習制度が抱えていた諸問題は2000年代に明るみになり、少しずつ外国人労働者の権利を守る動きが始まりました。2017年には「外国人の技能実習の適正な実施および技能実習生の保護に関する法律」(技能実習法)が施行され、違反した監理者は実名公表などの処罰が下されるようになります。問題の表面化から法整備が行われて以降、外国人労働者の処遇には、どのような変化が現れたのでしょうか。

「改善の兆しは見られるようになりましたが、相変わらず意識の低い受け入れ側も多く、よい職場にあたるか悪い職場にあたるかは『運』によって決まってしまうところがあります。その結果、技能実習生が当初の職場から失踪してよりよい仕事を探そうとするなど、いまだにトラブルは見られます。また2019年に特定技能という在留資格が創設されるのですが、これは外国人労働者にとって、とても大きな変化でした。それまで日本では単純労働を目的にした外国人は受け入れず、そういった仕事に就くのは技能実習生や日本人の配偶者がいる人、留学生などに限られていました。その方針を転換したのが特定技能になります。
これは、少子高齢化による人手不足が問題になっていることから、『もう建前と中身の乖離をなくして堂々と外国人の単純労働者を入れましょう』という方向に舵を切ったことで作られた在留資格です。また2024年には、1993年から続いた技能実習制度を廃止し、育成就労という新たな制度を導入するための議論が国会で始まる見込みです(※2024年5月9日現在国会で育成就労導入にかかわる入管法改定案が審議されているが、同法案では故意に税金を納めなかった場合などに永住資格を取り消す制度も提案されており、成立した場合は国による恣意的な適用が懸念される)」
クルド人に見る、外国人労働者と社会意識
外国人労働者に関する問題は世界的に議論が交わされており、特にヨーロッパでは極右政党が排外主義的な言動や行動をするなど、移民の受け入れに抵抗する動きが顕著になっているようにみえます。日本ではどのような声がインターネット上などであがっているのでしょうか。
「外国人の受け入れに関してはさまざまなデータがあり、その影響については一概に結論づけられるものではありません。とはいえ、外から人を受け入れることに対して、直感的に治安が悪くなると感じる人が多いのは事実です。また、『福祉が食いものにされる、自分たちの税金で運営されている生活保護を外国人に与えるな』といった意見は、世界的にもよく聞かれます。外国人も日本で働いたら同じように税金を払いますので、その理屈はもちろん誤りなのですが。なおアメリカやヨーロッパでは移民に仕事を奪われるという意見も多いのですが、これは慢性的な人手不足にあえぐ日本ではあまり言われず、社会状況の違いを端的に表していると思います」
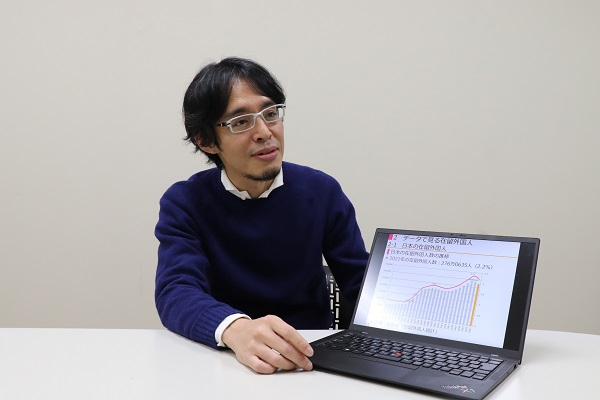
日本では2010年代以降、埼玉県南部にトルコでの迫害を逃れてきたクルド人の居住者が急増し、日本の外国人労働者問題を考える上で目が離せないエリアとなっています。蕨市と川口市に住むクルド人はおよそ3,000人、特に蕨市については「ワラビスタン」という通称も浸透しているようです。日本におけるクルド人コミュニティもまた、インターネット上で非難を受けることが多々あります。
「日本には大阪市生野区のコリアンタウンや神奈川県川崎市、愛知県豊田市など、外国人が集住する地域がたくさんあります。埼玉県のクルド人は、歴史も人も若いことからコミュニティ自体が不安定で、時折、地域でのトラブルが話題となることがあります。
こういった外国人コミュニティは、ある程度の世代交代により地域に溶け込んでいくのが一般的です。埼玉県のクルド人も日本語が堪能な若い世代が増えてきて、母国語しか話せない親と地域の橋渡し役を担っています。彼らは解体業を主な生業としており、今や都内の多くの解体現場で活躍しています。難民申請が受理されず仮放免の状況である場合が多い彼らが解体業を支えている状況を見ると、今の難民の認定制度が本当に正しいのか、改めて考えなおす必要があると思います」
明戸先生が語るクルド人への「仮放免」とは、本来入管の施設に収容されるべき人を役所の裁量で地域に居住させる仕組みですが、就労を含め多くの行動が制限されます。しかし、人手不足の日本では彼らの労働力に頼らざるを得ず、規定そのものが形骸化しているといいます。
「仮放免のクルド人は、法的には仕事もできず、許可がなければ県境も越えられないという状態です。しかし、現実に目を向けると、彼らは実質的に日本で働いており、この先も経済を支えてくれる可能性が大きい。そうなると、制度で縛り付けるよりも、在留特別許可を与える仕組みを積極的に適用するのが現実的ではないかと思います。実際アメリカやカナダ、フランス、ドイツなどでは、難民申請が日本よりもはるかに多く認定されています。今の日本のように申請したうちの1%しか難民として認められない、その上3回申請して許可されなければ強制送還という現状は、排外的なだけでなく日本の実態にも即していません。日本の入管は、実態に即した対応を行うべきだと思います」
豊かな社会を作るために必要な外国人労働者との共存
今後、さらに増加が見込まれる外国人労働者に対し、私たちはどのような姿勢で向き合うべきなのでしょうか。メディアによって流布されるイメージやSNSとの向き合い方も含めて課題となりそうです。
「ある程度メディアリテラシーがある人でも印象論の影響からは逃れ難く、たとえばニュース記事で『◯◯国籍の男が逮捕されました』という情報が出ると、外国人労働者全体の犯罪率が高いといった認識をもちがちです。国籍については必要な情報だから一切隠すのも違うと思いますが、これを見出しに入れることで国籍に対するイメージが大きくなり、必要以上に外国人が罪を犯している印象を植え付けてしまうおそれがあります。報道では不要な煽りをしないことが重要です。また、ニュースサイトのコメント欄は、ヘイトスピーチに通じるような空気が醸成されることが多く、ワイドショーなどが演出する空気感とともに鵜呑みにしないように注意すべきでしょう」
では今後、日本がより豊かな国へと発展するために、外国人労働者との関係は、どのように紡がれていくべきなのでしょうか。
「地方自治体で外国人労働者の問題に対応している担当者は、その地域での外国人の実態を理解し、外国人労働者なしでは社会が成り立たないことを把握しています。それを前提に多言語サービスなどを行っていますが、国が消極的だと、こういったサービスに予算が付かなくなります。また外国人全体の語学習得力を底上げするには、さまざまな団体がボランティアで行っている日本語教育などにも予算を追加する必要があるでしょう。
こういった提案には反対意見もありますが、日本語でちゃんとコミュニケーションできる外国人労働者がしっかり仕事をして経済的な余裕が生まれると、地元住民との軋轢は自然と減っていくはずです。先ほどの埼玉県のクルド人のケースなども、政府が外国人労働者に対して曖昧な対応を続けていると、いつまでたっても状況は変わりません。政治家も現実に沿った政策を打ち出してほしいと思います」

法整備が進み、日本が1990年代から30年以上抱え続けてきた外国人研修制度や外国人技能実習制度の矛盾が、今やっと解消されつつあるようです。皆が共存を進める上で、行政による制度や体制の見直しとともに、社会の中で彼らの立場や受け入れに対する関心や理解を広げていくことが大切になってくるでしょう。
プロフィール

経済学研究科 准教授
社会学を専門とし、社会思想、多文化社会論を研究。近年はヘイトスピーチ、レイシズムなど、排外主義の問題に取り組む。著書に『アンダーコロナの移民たち』(共著、明石書店、2021年)、『テクノロジーと差別』(共著、解放出版、2022年)、『レイシャル・プロファイリング』(共著、大月書店、2023年)など。訳書にダニエル・キーツ・シトロン『サイバーハラスメント』(監訳、明石書店、2020年)などがある。
※所属は掲載当時





