フィンランド人にとって、子どもは国の宝
日本では児童虐待問題の深刻さが、新たに公表された統計によって浮き彫りになっています。警察庁による最近の発表では、児童虐待の疑いで警察が児童相談所に通告した18歳未満の子どもの数は、2023年は12万2,806人(2024年2月発表)に上り、これは前年と比べて6.1%の増加、また統計が残る2004年以来19年連続で増加していることが明らかになっています。
「私は、児童虐待という社会問題と、多胎児(双子や三つ子など、一度の出産で複数生まれた子ども)の育児支援のあり方について研究してきました。多胎児は虐待のリスクが高いとされており、私が研究を始めた2007年頃は児童虐待事件が毎日のように報道されていました。多胎児家庭の虐待のリスクを低減するためには、妊娠中からの介入が効果的であると感じていたため、行政と協働して研究を進めました」と横山教授は話します。
虐待問題について研究を進める中で、横山教授はフィンランドのネウボラと出会ったといいます。ネウボラは、フィンランドにおける公的な母子保健サービスを提供する機関で、妊娠中の女性、乳幼児、そしてその家族を対象とした予防医療や健康管理、相談の場を提供しています。またこのシステムは、早期からの健康増進と予防介入を通じて、子どもたちのすこやかな成長と発達を支援し、児童虐待などの社会問題の予防にも貢献しています。
「私はヘルシンキ大学と国際共同研究を行っていました。あるとき、ヘルシンキ大学の研究者とのコーヒーブレイク中に、『日本の痛ましい児童虐待の現状をなんとか予防できないか』と話すと、彼らは口々に『フィンランドにはネウボラがあるから大丈夫だ』と言うのです。このやり取りがきっかけで、私はネウボラの研究を始めました」と自らの転機について振り返ります。
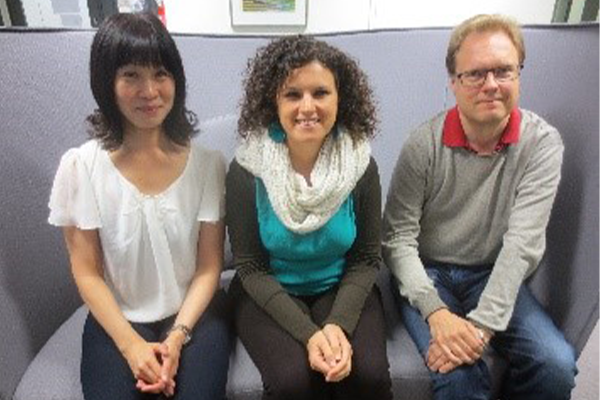
横山教授(左)とヘルシンキ大学の共同研究者
ネウボラの特徴は、同一の担当者(保健師)による家族全体への継続的な支援にあります。
そもそもフィンランドには、子どもを大切にする社会をつくっていこうとする考え方が、歴史の中で根付いてきたといいます。1917年にロシアから独立した後の貧しい時代でも、国が乳児のための育児用品をつめた育児パッケージを給付する制度を制定するなど、子どもたちを大切にする文化がありました。「フィンランドでは、第二次世界大戦中でも、子どものために衣類用の布を確保し続けました。戦時下の物資が少ないときにも子どもへの配慮を怠らないのには驚きます。こうした姿勢を反映しているのが、現在のネウボラのあり方だと感じます」と横山教授は話します。
そんなフィンランドでも、ひとり親家庭や、夫婦の一方あるいは両方に連れ子がいる中で再婚した家族(ステップファミリー)も多く、日本と似た状況だといいます。それでも、フィンランドの乳児期における虐待事件は極めて稀です。フィンランドで20年の経験を持つ保健師が、虐待が疑われるケースと出会ったのはわずか5件だったといいます。
「これは、国民のネウボラの保健師への信頼が非常に高く、継続的な家族支援が充実しているからこそ実現しています。日本では、担当保健師による子どもを持つ家族への継続支援についての理解がまだ浅く、フィンランドから学ぶべき点が多いと感じています。ネウボラのシステムは、虐待問題への対策だけでなく、子どもや家族への支援のあり方についても大きなヒントを与えてくれます」
家族全員へのケアを提供するネウボラ
私たちが学ぶべきシステムのひとつが、妊娠期間中のサポートだといいます。フィンランドでは妊娠を確認すると、妊婦やその家族は病院ではなく、妊産婦を対象とした「妊産婦ネウボラ」のサービスを受けます。このサービスの特徴は、妊婦だけでなく家族全員のケアを行い、同じ担当者が継続して支援するところです。

フィンランドの妊産婦ネウボラで利用される施設①

フィンランドの妊産婦ネウボラで利用される施設②
妊産婦ネウボラには、保健師や助産師が勤務しており、さまざまな検査、生活指導、夫婦関係の相談、避妊に関するアドバイスなどを提供します。フィンランドの出産後の入院期間は、通常1日半から2日程度と短いものの、保健師が1週間以内に家庭訪問を行うという特徴があります。
「日本では、妊娠が判明すると一般的に病院でのケアが中心となります。また、地域の保健事業は、事業ごとに異なる保健師や医師によるサポートが行われます。しかし、フィンランドのように同じ担当者による家族全体への継続的な支援や、妊娠から出産、育児に至るまでの一貫したサポートを実施している自治体は非常に少ないのです」と横山教授は話します。

さらにフィンランドには「子どもネウボラ」があり、保健師による乳幼児への個別健診を中心とした支援を提供しています。ここでは、生活スタイルや家族関係についてのアドバイスも行い、家庭訪問を通じて家族全体の支援を行います。特に、フィンランドの保健システムは、乳児期にほぼ毎月、1歳以降も少なくとも年に一度の定期健診を行い、家族全員を対象にした総合健診も実施しています。
これにより、子どもの心理的な問題や学習障害、過体重などさまざまな課題に早期から対応し、特にリスクの高い家庭にはさらに手厚い支援(ハイリスクアプローチ)を提供しています。
「日本の場合、集団健診が一般的で、4か月児健診や3歳児健診などが行われますが、フィンランドのように頻繁には実施されません。また、担当する保健師が異なることが多く、信頼関係の構築が難しい面もあります。さらに、日本の支援はハイリスクアプローチに偏りがちです。最近になって厚生労働省も見直しを進めていますが、ハイリスクアプローチに限定されないポピュレーションアプローチに重点をおいた、フィンランドのような支援にはほど遠いというのが現状です」
横山教授は、ネウボラの保健師へのインタビューも行ってきました。すると“父親を含めて家族全体を妊娠中から知っているため、信頼関係を構築しやすい”、“家族の抱える問題や課題に対し、些細な変化でさえも、担当保健師が把握できる状態にある”という回答が多かったといいます。インタビューの中で横山教授がもっとも驚いたのは、虐待やDVなどの問題を抱える家庭ですら、自ら助けを求めて、ネウボラの担当保健師のもとに訪れるという事実でした。「日本では、リスクが把握されてから家庭訪問が行われる場合がほとんどです。そのため、保健師が訪問すると住民は虐待を疑われているとの疑念を抱き、訪問を拒むことも少なからずあります」
島田市に見る、担当保健師制度の効果と現状
日本でもフィンランドのネウボラのような支援を導入している自治体があるといいます。
人口約9万7,000人、年間出生数600〜650人の静岡県島田市は、日本で先進的な担当保健師制度を実施している自治体です。2019年からすべての子育て家族に対して担当保健師制度を導入し、継続的な支援が行われています。
島田市には22人の保健師がおり、健康づくり課で母子保健を担当しています。担当保健師による初産婦とその夫を対象とした妊娠8ヶ月の面談や新生児訪問、7か月児相談など、一貫して同じ保健師が関わることで、子どもの成長過程を通じた継続的なサポートを可能にしています。
横山教授が島田市の保健師に行ったインタビュー調査によると、“担当保健師制度導入前はハイリスクケースに注力する一方で、その他の対象者への対応は以前の状況が分からずその場しのぎの対応にならざるを得なかった”と保健師が感じていたことが明らかになりました。しかし、担当保健師制度導入後は継続して対象者にかかわるため、潜在的な変化に気づきやすくなり、より積極的かつ個別の変化に応じた対応ができるようになったといいます。
さらに、担当保健師自身がこれまで以上にやりがいを感じるようになったそうです。横山教授の調査では、保健師自身も対人サービスの時間増加に伴う忙しさはあるものの、担当保健師制度により仕事のやりがいや楽しみが増え、スキルアップへの意欲も高まっていると感じているといいます。
「島田市におけるこの制度は、保健師と住民双方にとって大きなメリットをもたらし、より質の高い保健サービスの提供に繋がっていることが明らかです。この成功例は、他の自治体にとっても参考になるモデルといえるでしょう」
担当保健師制度による信頼できるマタニティ・ケアは、社会に安心を与え、児童虐待のような社会問題を未然に防ぐ可能性があります。さらに、そうした社会においては保健師の仕事はより実りのあるものになります。信頼の積み重ねがつくるマタニティ・ケアこそが、本当にすこやかな社会の根幹なのかもしれません。
プロフィール
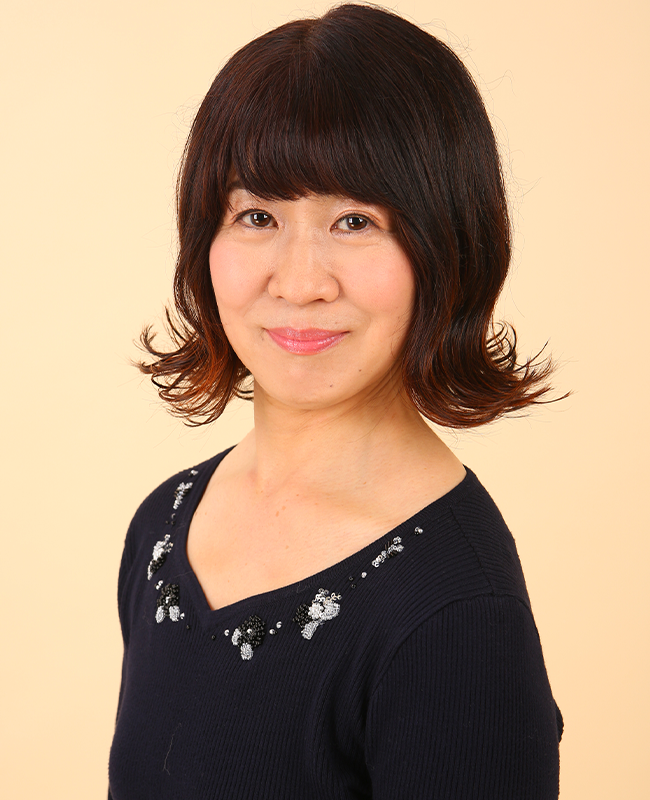
看護学研究科 看護学専攻 教授
博士(医学)。専門は、公衆衛生看護学、公衆衛生学、疫学。
千葉大学看護学部卒。2004年岡山大学医学部教授、2007年大阪市立大学大学院看護学研究科教授を経て、2022年より現職。2021年より内閣官房孤独・孤立対策の重点計画に関する有識者会議構成員、孤独・孤立の実態把握に関する研究会委員。2007年からフィンランド・ヘルシンキ大の客員研究員となり、双生児研究法を用いた共同研究を開始。また、フィンランド国立健康福祉研究所などと共同で、フィンランドの母子保健(ネウボラ)に関する研究を推進。『ネウボラから学ぶ児童虐待防止メソッド』(医学書院)など著書多数。
※所属は掲載当時





