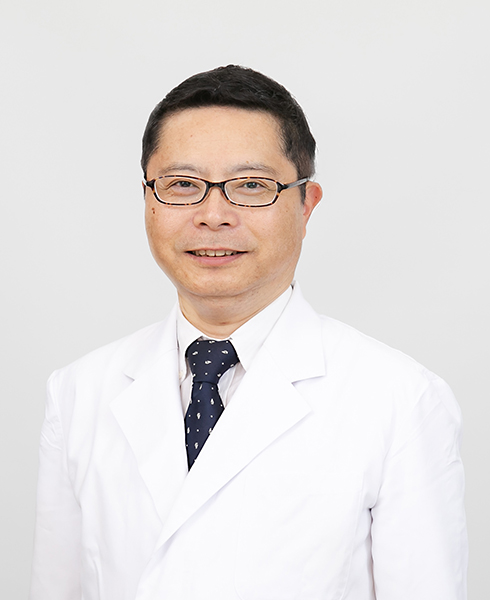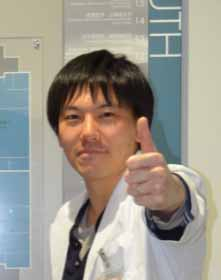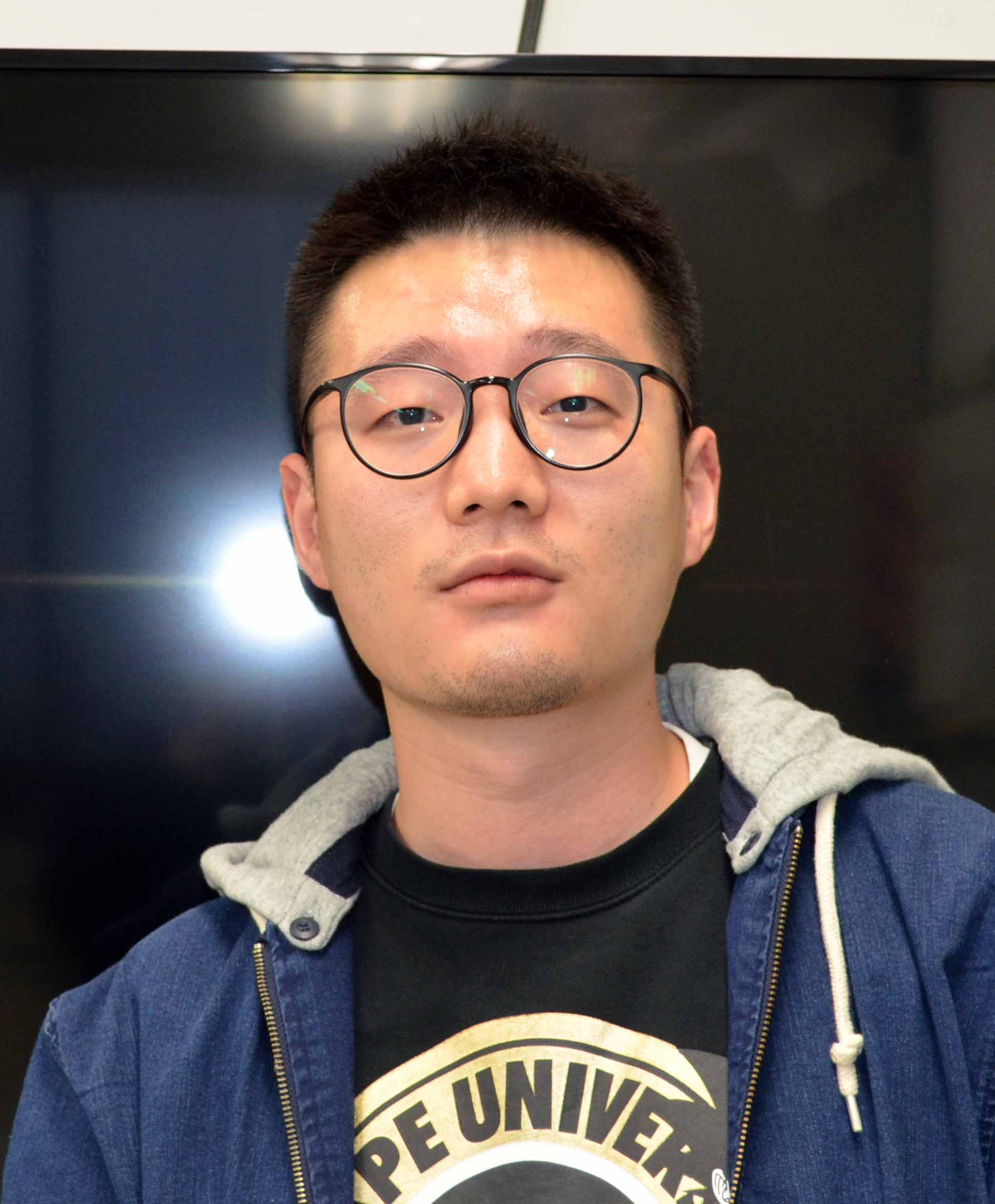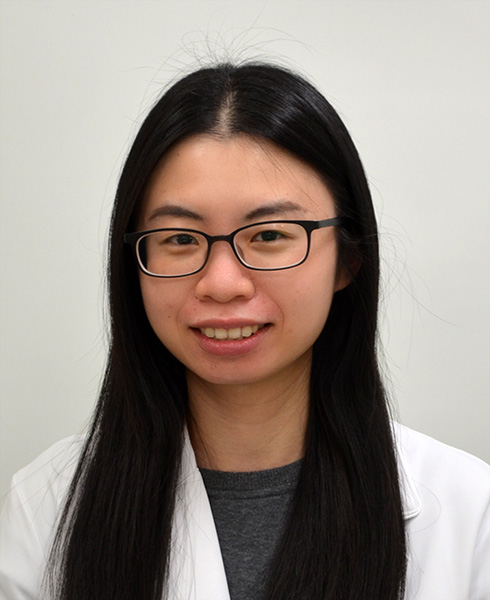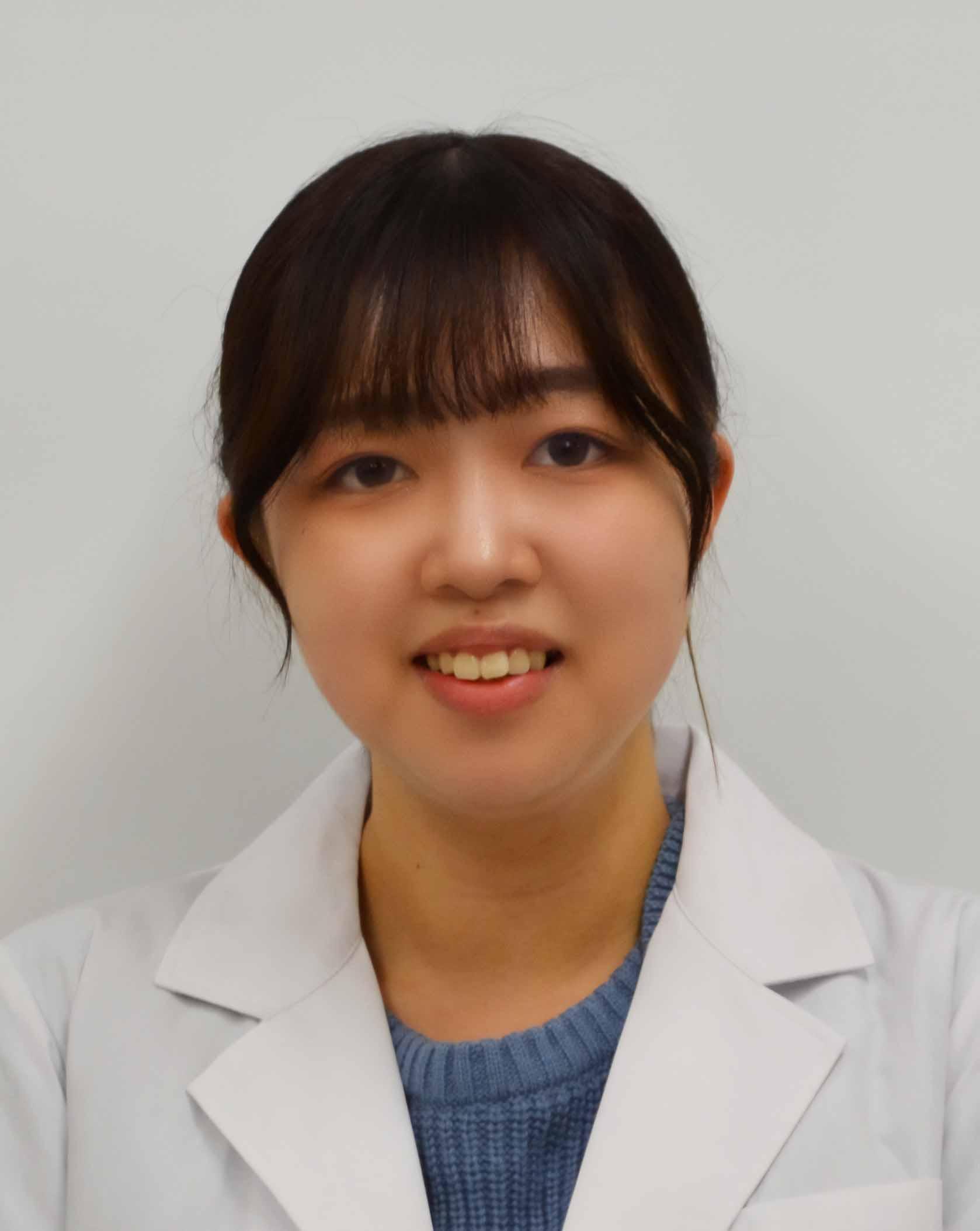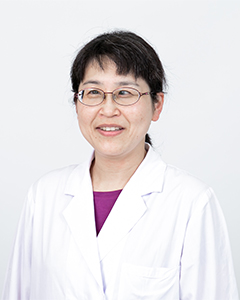環境リスク評価学教室にようこそ!


研究内容
 当教室では毒性病理学を基盤にし、分子生物学および統計学的手法を駆使して
当教室では毒性病理学を基盤にし、分子生物学および統計学的手法を駆使して
について取り組んでいる。
研究室では病理組織学的解析、分析化学的解析および分子生物学的解析手法を用いてin vitro、in vivo双方から研究を行なっている。
環境リスク評価学教室では、大学院生を募集しています。
 発がん研究に興味のある方
発がん研究に興味のある方
 がん予防研究に興味のある方
がん予防研究に興味のある方
 環境発がんリスク評価に興味のある方
環境発がんリスク評価に興味のある方
 毒性病理学研究に興味のある方
毒性病理学研究に興味のある方
経験・バックグラウンド等は問いません、がん研究に興味のある方は是非御連絡を。
ご希望の方は魏までご連絡下さい。
 環境中化学物質の発がんリスク評価および短期包括的評価モデルの開発 環境中化学物質の発がんリスク評価および短期包括的評価モデルの開発 |
|
ヒトは日常生活の中で様々な低用量の環境発がん性物質に暴露されながら生活している。また、ヒト発がんの原因の多くは喫煙や医薬品・食品添加物などであることから、それら物質の安全性あるいはリスクを評価するために、発がん性あるいは毒性影響について詳細な情報が必要である。当教室ではこれまでにいくつかの新規合成あるいは天然由来の化学物質について、動物実験モデルを用いて種々のリスクを報告している。
また、我々はより短期間でかつ包括的にリスク評価可能なモデルの開発を行なっている。
|
 有機ヒ素化合物による膀胱がん発生機序の解明 有機ヒ素化合物による膀胱がん発生機序の解明 |
|
当教室ではこれまでに有機ヒ素化合物ジメチルアルシン酸のラット膀胱への発がん性を明らかにしている。しかし、その詳細な機序については不明である。我々は分析化学的手法によるジメチルアルシン酸の生体内代謝物質の検索、さらに病理組織学的解析の結果から真に発がんに寄与する物質を同定している。現在、同定した物質の遺伝毒性の有無、種々の影響およびその機序について動物実験系を用いて解析を行なっている。
|
 有機フッ素化合物の発がん性評価と評価スキームの確立に関する研究 有機フッ素化合物の発がん性評価と評価スキームの確立に関する研究 |
|
有機フッ素化合物であるPFAS(Per-and Polyfluoroalkyl substances:パー及びポリフルオロアルキル物質は幅広い用途で使用され、環境中での難分解性及び生体内蓄積性が問題となっている。近年、国内複数地域の浄水施設の水道水から基準値を超える濃度のパーフルオロオクタン酸(PFOA)とパーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)が検出され、ばく露による有害性、特に発がんの健康影響が懸念されている。我々はこれまで既知発がん物質の大半が肝臓を標的にすることに着目し、遺伝毒性及び非遺伝毒性肝発がん物質を短期かつ高精度に検出できるスキームを確立した。本研究ではそのスキームを活用し、有機フッ素化合物の肝発がん性検証とともに、新たに有機フッ素化合物に特異的な肝発がん性評価スキームの開発を行っている。
|
 不死化ヒト細胞株を用いたヒトへ外挿可能な毒性評価モデルの確立 不死化ヒト細胞株を用いたヒトへ外挿可能な毒性評価モデルの確立 |
|
動物実験系において得られた毒性および発がん性試験データをヒトへ外挿させる際に、ヒトとげっ歯類をはじめとした実験動物における代謝系やその応答の差異が化学物質のリスク評価を難しくさせている。そこで本研究では、ヒト由来細胞株に不死化遺伝子セットを導入した不死化ヒト細胞を樹立し、それらを用いたよりヒトの病態を反映した毒性評価モデルの確立を目指している。
|
 臨床への取り組み 臨床への取り組み |
| 動物実験系における発がん機序の解析あるいは遺伝子・蛋白の網羅的解析によって得られた機能遺伝子・蛋白およびマーカー遺伝子・蛋白について、その有用性についてヒト臨床材料を用いた解析を行い、腫瘍発生過程における早期診断マーカーあるいは予後予測マーカーの開発に寄与するデータの蓄積を行なっている。 |
教室員
 |
PI
研究教授
魏 民
Min Gi
|
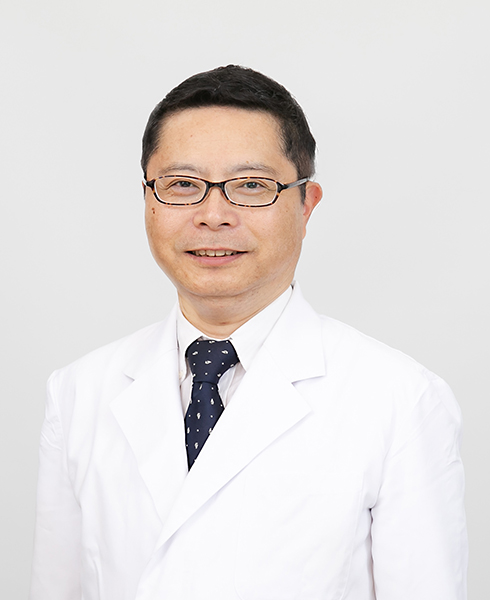 |
特任教授
鰐渕 英機
Hideki Wanibuchi
|
 |
特任助教
ワチラアルンウオン
アルパマス
Arpamas Vachiraarunwong
|
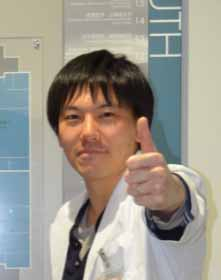 |
研究員
山野 荘太郞
Shotaro Yamano
|
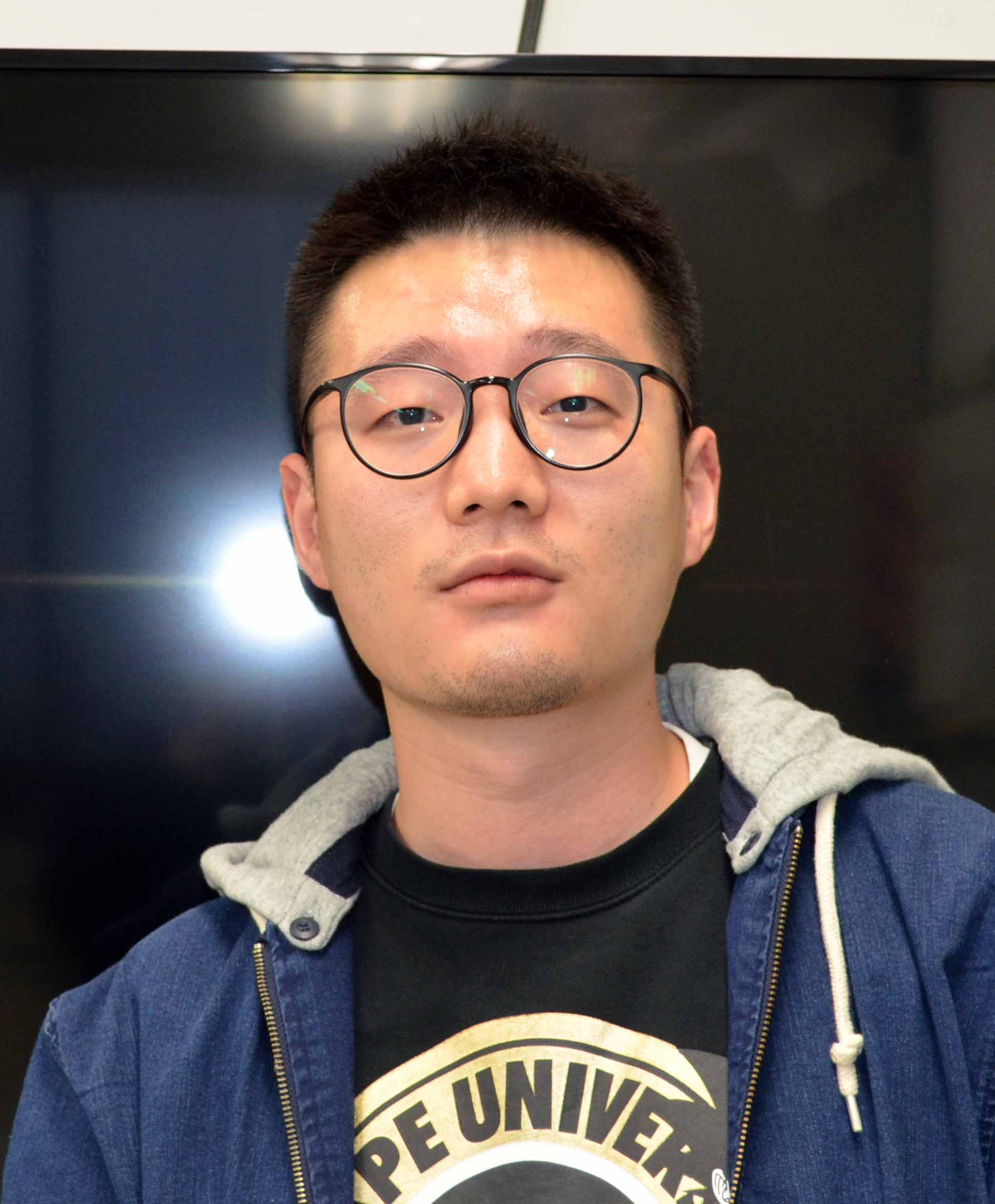 |
大学院生 博士課程3回生
郭 潤傑
Runjie Guo
|
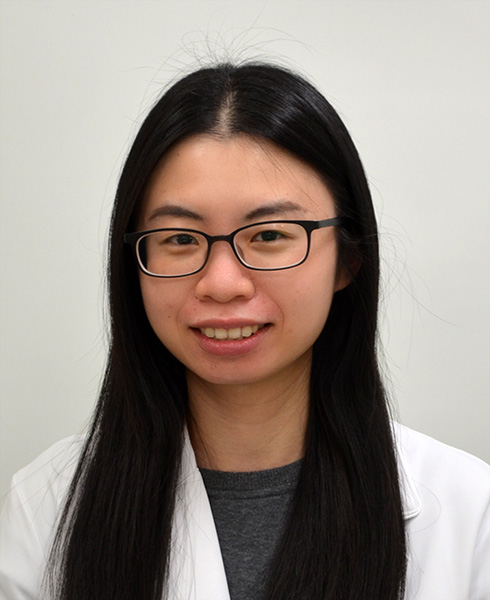 |
大学院生 博士課程3回生
邱 桂鈺
Guiyu Qiu
|
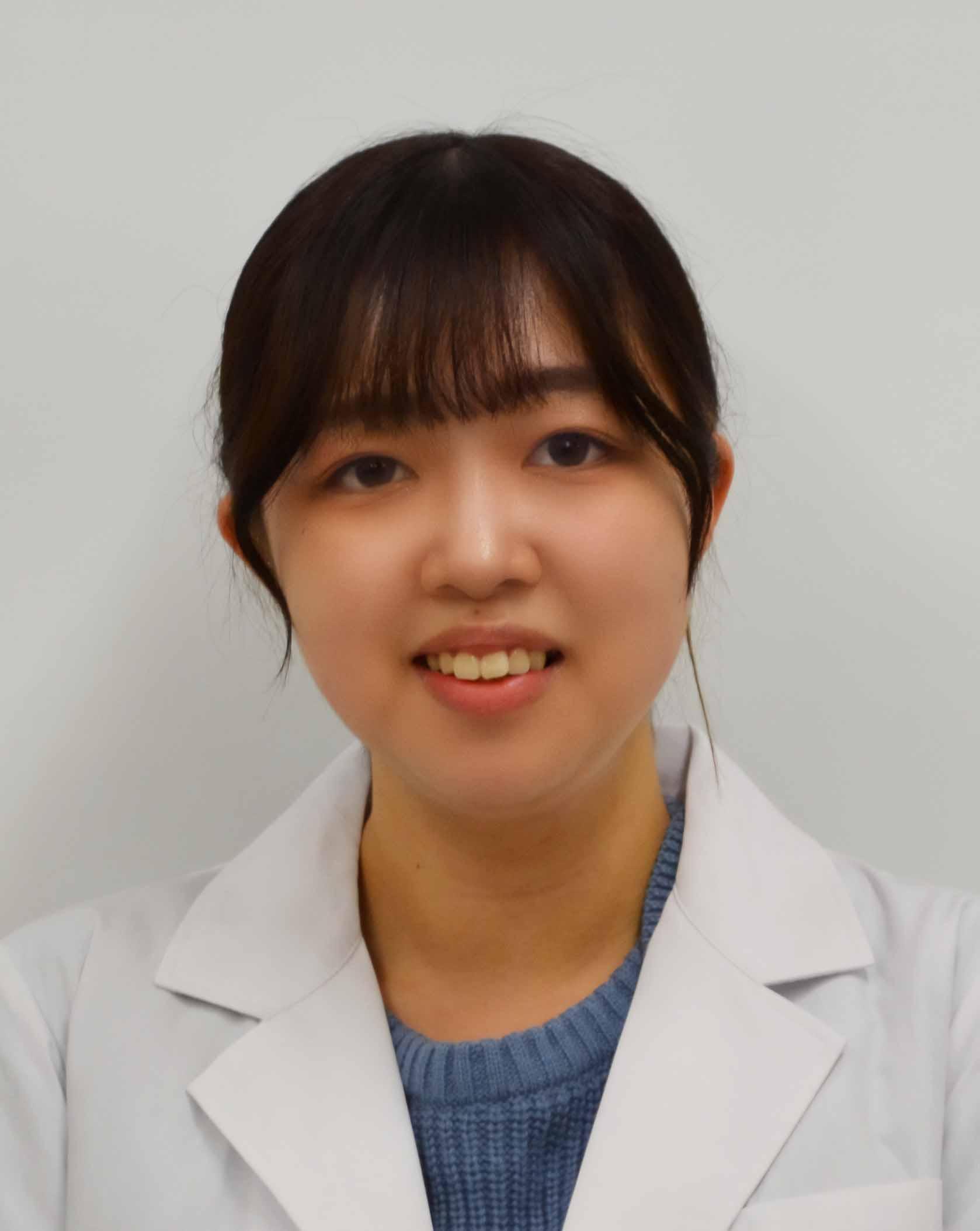 |
大学院生 修士課程1回生
河村 百合菜
Kawamura Yurina
|
|
|
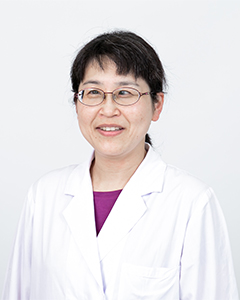 |
研究補助員・実験助手
小野寺 利枝
Rie Onodera
|
 |
秘書
井浦 孝子
Yukiko Iura
|


![]() 当教室では毒性病理学を基盤にし、分子生物学および統計学的手法を駆使して
当教室では毒性病理学を基盤にし、分子生物学および統計学的手法を駆使して![]() 発がん研究に興味のある方
発がん研究に興味のある方![]() がん予防研究に興味のある方
がん予防研究に興味のある方![]() 環境発がんリスク評価に興味のある方
環境発がんリスク評価に興味のある方![]() 毒性病理学研究に興味のある方
毒性病理学研究に興味のある方